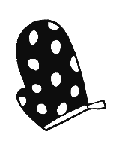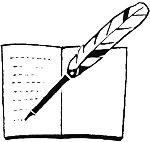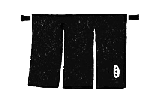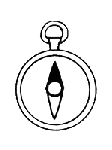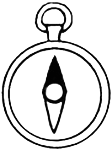さまざまなウェブメディアや
『anan』『婦人画報』などの人気雑誌で執筆する他、
ご自身のBLOG『京都くらしの編集室』で京都ライフを発信している
京都在住フリーライター・江角悠子さん。
彼女ならではの視点で
京都のおつけもん屋さんを訪ね歩きます。
お店の個性やオススメの逸品、
ありきたりじゃない京のおつけもんが揃っています。
ツウな情報をお楽しみください!
京都ライター江角悠子の
京都おつけもん探訪記
Kyoto Otsukemon Exploration



Part.24
村上重本店
Murakamijyu Honten
江戸時代の天保年間(1830〜1843年)に創業。180年近い時が経った今も当時と変わらず、西木屋町四条を南に下がった京都随一の繁華街にお店を構えています。今回は2年前に跡を継ぎ、8代目となった村上亮平さんにお話を伺いました。

看板には千枚漬の文字。のれんにある「丸に十文字」の紋は、薩摩藩島津家のもので、薩摩の殿様が村上重の漬物を食べ感銘を受け、紋の使用を許されたという。
「看板に “千枚漬”とあるように、元々は千枚漬を提供できる冬の間だけのお店だったんです」と村上さん。なんと!先代であるお父さまが店を継ぐまでは、冬の3ヶ月のみ営業をしていたそう。「父が店を継いだ頃、百貨店さんともご縁があって、通年お客様に提供できるお漬物を取り扱うようになり、年間通してお店を開けるようになりました」。そして今では季節ごとに内容がを変えながら、常時約40種のお漬物が並ぶようになったのです。



風情ある京町家の雰囲気が残る店内。のれんや置物など、季節が感じられるしつらいが素敵。この空間に身を置いて、お漬物をあれこれ選ぶ時間も楽しい。
店舗のすぐ横に工房があり、8代目を継ぐ村上さんも日々、現場に立っています。「市場での野菜の目利きをはじめ、職人さんに交じって漬ける作業にも取り組んでいます。漬け方は昔から漬物作りを担ってくれている大番頭さんから習い覚えました。材料や調味料に決まった量や重さはなく、そのときどきの野菜の状態を知り、手に感覚を覚えさせ、漬け込んでいます」。それにしても、こんな都心部の一等地に工房があり、昔と変わらず漬物づくりがされているとは、驚きです。
同店の千枚漬の特長は、通常使われる酢や砂糖、みりんなどを使用しないことにあります。原料は、昆布・塩・かぶらだけ。その代わり昆布へのこだわりは強く、粘りが強いもの、コクがあるものなど昆布の特長を見極め、数種類をブレンドして漬け込んでいるそう。「昆布については産地はもとより、昆布の切り方にまで工夫をこらして、 昆布の旨味が最大限に出る方法を用いています」と村上さん。原料がシンプルなだけに、素材の善し悪しが味に直結します。時代が変わり、昔ながらの素材が手に入り難くなってきた今、課題は「いかに良質の素材を集めるか」だと話します。同時に「受け継がれてきた味を守るために、変えていかなければいけない部分もある」とも。伝統にばかり固執するのではなく、現状を知り、しなやかに変化を受け入れていく村上さん。歴史ある老舗を背負って立つ代表という立場ながら、気負いのない自然体な捉え方。その姿勢こそが、店が長く続いていく秘訣なのかもしれない。お話を伺ってそう深く感じ入ったのでした。


イチオシ商品

千枚漬
1袋 1,000円(税込)
酢やみりんを使わない、甘くない千枚漬。昆布を数種類使っているだけあって、袋から出したときの粘りがすごい!かぶらは厚めにスライスされており、食べるとシャキシャキとした歯ざわりが心地いい。創業以来変わらないというレトロなパッケージデザインも魅力。11月初頭〜2月末だけ味わえる特別な商品です。
ライター江角の


村上重本店
京都市下京区西木屋町四条下る船頭町190
TEL 075-351-1737
営業時間 9:00~19:00
(土・日・祝日は17:30迄)
年中無休(元旦から3日を除く)
https://www.murakamijyuhonten.co.jp/



.png)